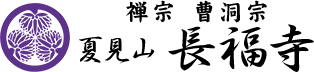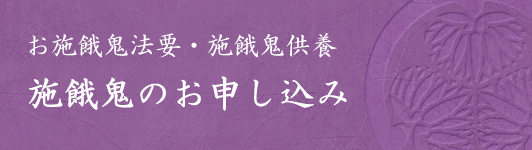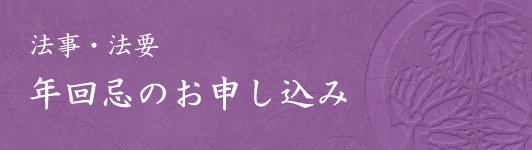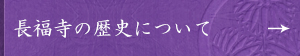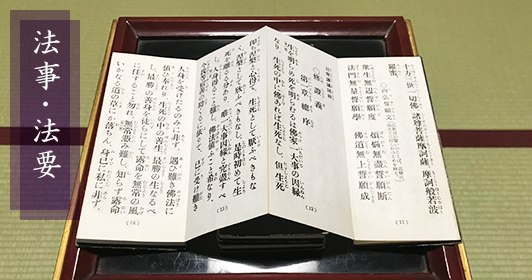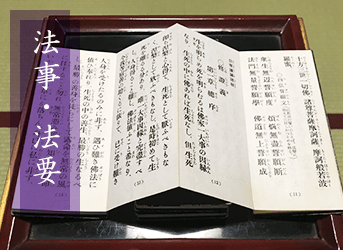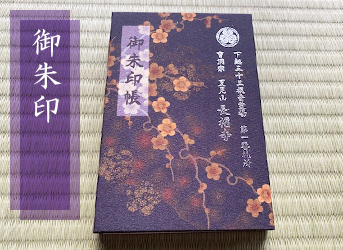アクセス
お寺へのアクセス
〈JR 船橋駅北口より〉
【バス】
京成バス千葉ウエストバスターミナル内4番の医療センター経由バスにお乗りいただき「長福寺入口」停留所にて降車後、徒歩2分です。
【タクシー】
およそ5分~10分で来山可能です。(近隣に同名の寺院がございますので、必ず夏見(なつみ)長福寺と申し伝えて下さい)
お寺から墓所まで
長福寺より徒歩5分の場所に、当山が運営している約200区画の「船橋夏見霊園」がございます。
紫色が徒歩で向かわれる方、青色はお車で向かわれる方のルートとなります。